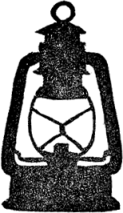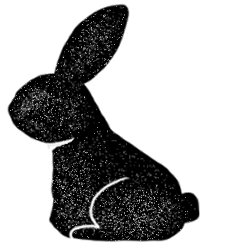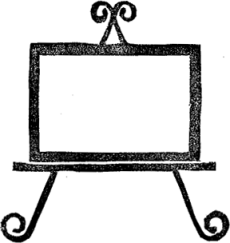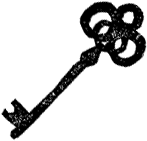最近、男は妖精と二人暮らしを始めた。
本当に妖精かと問われると、自信はない。そう彼は答えた。
久々に訪れた裏路地の市場で、彼が「日々の生活に困らない程度に金を持っている無職独身」と知っている商人に無理やり押し付けられたからだ。
「幸福の妖精だとか。今までの持ち主はみな、大願を成就させたって話で」と言って渡されたアンティーク調の鳥籠には、その売り文句の胡散臭さを補強するように、幾重もの純白のレースで覆われていた。
「だったら君が持っていればいいだろう」
「そりゃそうなんですけど。聞いたことのない言葉を喋るから、気味が悪いってもんで」
商人から渡された鳥籠はずっしりと重い。提示された金額は、意匠を凝らした鳥籠の対価だと思えばはした金だった。
書斎の机に鳥籠を置いて、小窓を開ける。吹き込んだわずかな風が、目隠しのレースを小さく揺らした。
たっぷりと重ねられた繊細なレースは花嫁の纏うヴェールか、閨の天蓋か。ともかく、おいそれと触れるのは憚られた。このまま風が捲り上げてくれないものか。しばらく遠巻きに眺めていたが、今日の風は花嫁の秘密を暴く勇気はないらしい。
「そういえば世話の仕方とか、何も聞かなかったな。こいつ、何食べるんだ?」
おおかた、人の言葉を真似る鳥に他言語を仕込んだのだろう。ペットショップでエサを見繕ってもらうとして、とりあえずは、水か?
『いらない。かわりにあなたの望みを聞かせて』
キッチンに向かう彼の耳元で何かが囀った。この地域の言葉ではないが、意味は理解できた。
ぎょっとして振り返ると、いつの間にか鳥籠の扉が開いて、レースの覆いも捲れあがっている。右肩に気配があった。反射的に手で振り払うが、何かに触った感触はない。頬の近くを何かが素早く横切ったような空気の流れを感じた。
視認すらできないそれを捕まえることを早々に諦めた男は、引き出しから翻訳機を取り出した。よく似た言語体系の星があったな、と独り言を言いながらデバイスを調整する。
「妖精? 本当に?」
たどたどしい言葉で、彼は虚空に話しかけた。ややあって、答えが返ってくる。
『nsdf;:@g』
音と認識はできるが、言語として検知できない。男が無反応になると、それはまた別の言語で言葉を発した。
『あ……な、たの望みは?』
それ以来、男はこの妖精と暮らしていた。妖精本人から妖精だという宣言がないので、呼び名は便宜上の仮称だ。
確かに、望みが叶うようになった。といっても、大したものではない。いつも固くて難儀する瓶の蓋が簡単に開けられたとか、億劫だと思っていた問題がいとも簡単に解決されたとか、酒が無くても眠れるようになったとか。ごくごく些細な幸運が舞い込んだ。
それでも妖精は彼に問いかける。『本当の望みは?』と。「特にない」そう答えると、不満そうにレースの覆いをバタバタと揺らした。
「望みなんて、持ってちゃいけなかったんだよ」
決まって、彼は唱えた。
一人と一匹の生活はしばらく続いた。試しに手を出したギャンブルが散々な結果に終わったところで、この妖精について、男は一つの確信を得た。
向かったのは、いまや古都と呼ばれる歴史ある街だった。「不思議を集める」「探し物が見つかる」、そんな謳い文句の店ができたらしいと同僚に聞いたことがあった。先に「怪異専門の探偵事務所」を訪ねたが、もぬけの殻だった。移転しました、という張り紙にぶら下がっていたのがこの店と思わしきショップカードだった。
人通りもなく、生活の匂いもしない静寂の街並みを、大雑把な地図を頼りに歩き続ける。道がわからなくなったときは、妖精が騒ぐほうへ進めばよかった。空間ごと時代に取り残されたような古めかしい建物が立ち並ぶ裏路地の奥に、その店はひっそりと存在していた。
目印だという梟のドアチャイムも一致している。元々店として建てられたわけではないようで、ショウウィンドウも覗き窓もなければ看板すらもなく、中の様子を伺い知ることはできない。重厚な木製のドアについたランプが灯っているから、営業中、ということだろう。そもそも店かどうかもわからないのだけれど。早く入れ、と言わんばかりに鳥籠が激しく揺れる。
恐る恐るドアノブに触れるが、扉が開く気配はない。今度はドアノブを軽く押し下げる。モーター音は聞こえない。まさか、この主星に完全手動の扉が残っているとは思わなかった。重たい上に建て付けが悪いのか、手の力だけでは進まない。体重を預けるように押し開けた。たかが扉一枚に苦戦する男を嘲笑うように、梟を象ったドアチャイムが能天気に鳴いた。
「こんにちは」
どこかから凛とした女性の声が聞こえた。窓のない店内は薄暗く、いくつかのランプが穏やかな光を放っているだけで、声の主の姿は見えない。男は暗順応を待ち、店内を進む。カウンターから姿を現した女性の顔を見て、息を飲んだ。妖精が飛び出してまとわりついたのか、彼女の髪がふわりとそよいだ。柔らかな桃色と、その奥の蒼い瞳があらわになる。勘違い。他人の空似。あるいは子孫。いや、幻覚かも。
「いらっしゃい」
思考を巡らせていると、突然、真後ろから声がかけられた。あの重い扉が音もなく開いている。差し込んだ陽の光を後光のように背負った男性は、驚きで声が出ない男から鳥籠を取り上げた。逃がさないよ、と言わんばかりに。
「どうしてここへ?」
カウンターに鳥籠を置き、男性が――この店の店主が尋ねる。空気を震わせる、低く深い声だった。
全てを詳らかにせよ、と迫る紫の瞳に観念して、男は妖精との一部始終を語った。この妖精が、おそらく、行き場を失ったサクリアの集合体であること。以前、「不思議な店がある」と聞いてきたということも。
「サクリアはもともと、人々の希求に呼応するもの。だから、これは持ち主の望みを聞き叶えようとするのだろう、と」
「これの正体がわかっているなら」
長い指が滑らかな手つきで閂を外す。檻から解き放たれたそれは、空を切って店の中を、正確に言うと、店主の隣に立つ女性の周囲を飛び回る。妖精の姿が見えているのだろう、彼女は虚空に手のひらを差し出して聖母のような微笑みを浮かべた。
「これで適当な研究成果を出して、王立研究院に戻ればいいだろう」
「ああ……私のこと、ご存じだったのですね」
もちろん、と彼が頷いた。
「一応、聖地勤務の研究員の顔と名前は憶えているつもりだよ。みな、大事なパートナーだからね」
よかったら、とコーヒーを差し出して、店主はウィンクを飛ばした。礼を言ってゆっくりと口に含む。酸味の少ないまろやかな豆だった。あの頃もランチミーティングの度にコーヒーを振る舞われた。陛下が女王候補だったころに贈られたサイフォンだ、などという惚気話とともに。
鼻腔に抜ける穏やかな芳香に絆されて、人は本音を漏らしてしまうのかもしれない。男は意を決して、大きく息を吸い込んだ。
「神鳥への統合を機に故郷の星に戻ったんです。誰も、居ませんでした。当たり前ですけど。あんなに守りたかった故郷なのに、私の家族も知己も誰も存在しないと実感した途端、故郷も、自分の仕事も……貴女たちが命がけで救った宇宙が、無価値だと感じてしまった」
震える指をコーヒーカップから引き剝がし、カウンターに手をついて、頭を垂れた。一国の首長をも超越する権利を有する研究員は、公平無私の精神を以て職務に取り組まなくてはならない。
「故郷に執着なんて、望みなんて、持つべきではなかったのに、私は」
「今の私たちは、あなたに傅かれるような立場ではありません」
顔を上げて、と微笑む女性は玉座にいたころの何ら変わりがなかった。移動を終えた後、男が出奔する以前に聖地から降りているにもかかわらず。
「陛下……いえ、アンジュ様、ロレンツォ様。貴方達は、ここで一体、何を」
「長い神鳥の歴史において、宇宙の移動、というのはそう珍しいことではないそうだ」
店主が空になったカップに新たなコーヒーを注ぎ足した。実際、現在の宇宙も、現女王陛下の就任時に生み出された新しい宇宙だとされている。
「だが、元々ある宇宙に別の宇宙を統合させる、というのは例を見ない試みだった」
ミルクを注いでかき混ぜる。漆黒と乳白色が拡散して混ざり合った。
「リスク検証には君も携わったね」
「はい。一番危険視されていた移動時の重力干渉ですが、亜空間を一時的に利用することで解消しました」
カップを受け取った男はシュガーポットから星型の砂糖を取り出して、薄茶色の液体にぽとりと落とした。深煎りの苦みがにもう少し甘さが欲しくなり、さらに一粒放り込む。
「双方の研究院の尽力で、懸念事項はほぼ解決しました。ですが、私たちのサクリアだけは」
優れた研究者でもあった女王補佐官が、シミュレーションは行っていた。だが、何百回と試行を繰り返してもその結果は覆らない。
――彼らはその身に宿すサクリアが消えるまで、何百年、何千年と日々を繰り返し続けることになるだろう」
とある守護聖はあっけらかんと応える。「大丈夫。僕らはもともと、そういうモノだから。未練とかないんだよね」
「彼の言葉に、我々も覚悟を問われたような気がしました」
そして、彼は故郷に戻り、自分が正しく、ただのちっぽけな人間であったことに絶望した。
男が冷めきったカップを煽る。冷えて析出した砂糖が舌に残って、ジャリ、と嫌な音を立てた。
「私たちのサクリアはまだ無くなっていません。このまま緩やかに神鳥の宇宙に拡散していくと思われます。ですが、その過程で神鳥の由来のサクリアと反発したり、局地的に飽和してしまうことがわかりました。サクリアの生み出す歪みによって、様々なトラブルが起き始めています」
いつのまにか戻ってきていたのか、妖精が自己主張のように鳥籠のレースを揺らした。「あなたみたいな可愛らしいトラブルで済めばいいんだけど」と女性がレースに触れた。
「ここは、令梟のサクリアが起こす様々な事象を調査・解消するためのラボだ。極秘、というわけではないが彼女の私設機関ということになっているから、君達が知らなかったのも無理はない」
「別に秘密にするつもりはないんですけど、人手がほんとに足りなくて。こちらの研究院の手を借りるのも申し訳ないから、手弁当でやるしかなくなっちゃったの」
事業統合したらリストラで余剰人員が出ると思ったのに、と女性が口を尖らせた。
「まさか、くだんの探偵事務所というのも……」
「あっちはカナタとシュリが担当してる。今はレイナにも手伝ってもらってるけれど。ユエとノアはジュリアス様達と連携を取りながらトラブル対応に当たってる」
「ゼノはこちらの王立研究院にいるよ。ヴァージルは軍に招かれていたね。あまり、乗り気じゃなさそうに見えたけど」
「ミラン様とフェリクス様は、こちらに?」
「いいや、彼らはサクリアの対処をしながらそれぞれ旅をしているよ」
「はあ……意外なような、そうでもないような……。というか、皆様にまだそんな苦労をさせていたなんて」
てっきり自由な暮らしをされているのかと、と頭を抱えた彼を見て、店主達は顔を見合わせた後、にこりと口の端を吊り上げた。
「ということで、君。古巣に戻る気が無いなら、うちの外部調査員というのはどうだろう。定期的に調査報告書を送ってくれるだけで構わないから」
「お給料は前職基本給の七割に成功報酬でお願いできますか? 結構経費が掛かるんですよね。移動が多いし。あと、このレースは買い取らせてもらえる?」
畳みかけるようなスカウトと提示された金額に男は恐縮し、これはコーヒー代として、と鳥籠から外したレースを差し出した。
そんな金額を払ってるから経費が膨らむんですよ、とは口が裂けても言えなかった。愛おしそうにレースを撫でる元女王とそれを眺める元守護聖の表情から、それが二人の特別な何かであることは明らかだった。
とんとん拍子に再就職が決まり、「満足したらそのうち消えるだろう」と悪霊のように言われた妖精と男の共同生活も続くことになった。
「え、これ、回収しないんですか?」
「本人に離れる気がないなら仕方ないだろう」
「サクリアは呼応しあうから、サクリアの歪もその子が教えてくれるでしょう。ただ、ずっと鳥籠の中にいるのは嫌みたい」
いや、お前勝手に出て来てるだろ、という言葉は飲み込んで、男は入り口の扉に手をかける。扉はあっさりと開いた。カランカラン。軽やかなドアチャイムの音が、茜色に染まる静寂の街に響いて消えた。
『ねえ、望みはみつかった?』
「そういえば、そんな触れ込みの店だったか」
顔の周りをヒュンヒュンと飛び回る風切り音が耳障りで、男は大きなため息をついた。
「それで、いつまでいるんだ、君は」
『……そのうち?』
「そのうち、って」
悠久の時を生きる彼らの「そのうち」がどれほどのものか。
「まあ、ほどほどなところで成仏してくれたらいい。それが当面の望み」
彼の答えに満足したのか、飛び回りつかれたのか。キィ、と音がして鳥籠の扉が閉まった。
「名前、決めるか。妖精のままじゃ不便だから」
いくつかの候補を挙げながら石畳を進む。ふと来た道を振り返ると、ゆるやかに迫る暗闇が彼らの店を飲み込み始めていた。
「せっかく檻から出られたのに、また戻るなんてな」
思わず零れた独り言をかき消すように、男は小さくため息を吐いた。
店先の仄かな灯りが消えるのを遠目に見届けて、男と妖精は再び家路についた。